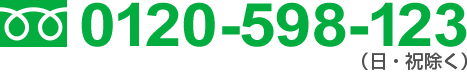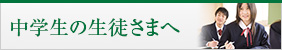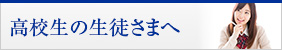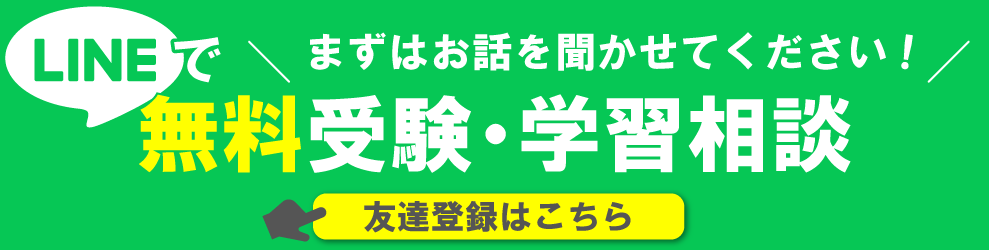本日は、勉強のやり方について、一つの提案をしたいと思います。
それは「インプット型」の学習と「アウトプット型」の学習を区別することです。この話は大学受験生(特に来年度受験生となる現高2生)を念頭において書いてみます。

入学試験というのは、なかなか厳しいもので、ある一日を境に勝ち負けの判定が下り、中間がありません。「頑張った」とか「惜しかった」といったことが意味を持たないという点で、学校の定期テストとは種類が違うものだと思わざるを得ません・・・と思ったのは受験生の立場に立たされた当時17歳の私。ライバル達に比べて圧倒的に不利な立場にあった私は、薄い可能性の中で「勝つ」道を見出す必要がありました。
以下は私の経験をベースとする話となるので、相当主観的なものになると思います。また、そもそも最適な学習法というものは人それぞれであろうとも思われ、こんな考えもあるんだと何かの参考になれば幸いです。
「インプット型」の勉強・・・「力」をつけるための勉強

ポイント
① 事前計画を立てること
② 一歩一歩前進しているという自覚と共に進めること
普通イメージされる勉強です。数学であれば、教科書に出てくる概念の定義、公式の理解、典型な解法の習得といったことで、当り前と言えば当り前でのことですね。ただこのとき、ひとつマスターすればその分は確実に進歩したという強い自覚を持つこと。英単語ひとつにしても、覚えれば覚えた分は確実に向上しているのです。一歩一歩前に向って進む、その一歩一歩をおろそかにしない気持ちが結局は長い道のりを歩かせてくれる気がします。
「力」がなければ話にならないので、学習の大半は「インプット型」でなければいけません。道のりは遠く、効果もすぐには出ないでしょう。そこで大事なのは先に学習計画を立てることです。教科ごと項目ごとに目標を設定し、テキストと月ごとの進捗スケジュールを決めておきます。受験勉強は長期戦です。道中不安に駆られることもありましたが、これをやれば大丈夫と自分で決めたことなので、幾分かは迷いを減らすことができたように思います。もちろん、計画通りに進まなかったり、項目によっては、これは違うのではないかと思ったりすることもありましたが、先に計画を立てていたからこそ、その修正は容易であった気がします。
「アウトプット型」の勉強・・・「力」を「点」にするための勉強

ポイント
① いわゆる「傾向と対策」の場合、狙いを持って行うこと、時間をかけ過ぎないこと
② 通常の学習の場合、「インプット型」の学習と区別して行うこと
いわゆる「傾向と対策」、これは特に受験勉強後半に必要となる入試対策固有の作業です。こと大学入試においては受ける大学によってその出題の在り方は様々です。正に個別であるために、一人ひとりその時の自分の状況に応じて工夫をする必要があります。
赤本をやるにしても漠然とやらない方が良いと思います。一回やってみた結果から自分の課題を見出し、その対策をしてから次の回をやってみるのが理想。過去問を解くこと自体は「アウトプット」の作業であり、それだけでは力をつけることになっていないことを知る必要があります。「アウトプット型」の勉強は狙いを持って極力効率的にやり、その結果を「インプット型」の学習にフィードバックさせるようでありたいものです。
あるいは模試。学校が受験機会を用意してくれるので何となく受けてしまいがちですが、場慣れする機会ぐらいの認識で受けるのでは勿体ない。前回の模試で「場合の数・確率」が出来なかった人は、次の模試までにその対策を進め、成果を次の模試で測定しては如何でしょう。また、高3になると、共通テスト模試(マーク模試)を何回か受けることになります。共通テスト英語(R)においては、80分で膨大な英文を処理することが求められ、時間不足に常に悩まされます。そこで各回の模試で、解く順番を変える、見切りのタイミングを早めるなど、新たな試みをもって臨んでは如何でしょう。これをいきなり本番で試すのはリスクが大きすぎます。実際に点を取らなければいけないのは本番だけなのであり、模試はそれを実現するための手段と捉えましょう。
直接の入試対策だけでなく、通常の学習でも、「インプット」と「アウトプット」の違いを意識した学習は大切です。
数学で、かなりの頻度で解答や解説を横において勉強する生徒を見ます。習い始めの段階では様々なチャネルから教わることになりますが、その段階を終えた後は、まずは自分の力で問題が設定する状況の意味を理解し、習い覚えた公式や解法をツールとして、解に至る道筋を構想する練習が必要となります。苦労の末に解を発見してこそ力もつくし、数学の問題を解く楽しさも分かろうというものです。
英語のリーディング演習では、長文を一回読み、読み終わったらもう一回読みます。2回目は一回目に比べて理解度が何パーセントか上がっている筈です。その上昇分は、一回目に気づかなかった何かに2回目で自力で気がついたということであり、こうした経験の蓄積が力となっていきます。単語や文法を調べたり覚えたりするのはその後の作業となります。
如何でしょうか。恐らく何が正しいというものは無く、それはその人のスタイルや志望校のレベルとの乖離度といった状況により決まってくるものでしょう。しかし、受験学年を迎える前に自分に合う学習方法を見つけておくことは大切であり、本稿が何かのヒントになれば幸いです。末文ながら皆様の受験の成功をお祈り申し上げます。
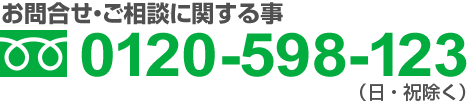

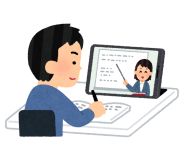 オンライン授業の可能性について
オンライン授業の可能性について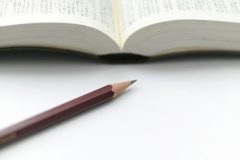 集中力も養う、テスト勉強のやり方と効率の良い勉強方法をご紹介!
集中力も養う、テスト勉強のやり方と効率の良い勉強方法をご紹介! 受験生の学習リズム―睡眠で大切な3つのポイント
受験生の学習リズム―睡眠で大切な3つのポイント トイレで見かけた英語2題
トイレで見かけた英語2題